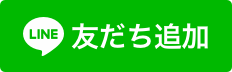借地権の相談
借地について、わからないことについて相談にのりたいと思います。
借地についての相談で多いです。例えば、借地権は売買できるのか?
借地の期間がきたら、賃貸みたいに更新できるのか。
借地を売却するときは、どうしたらよいかなどです。
借地権とは・・・借地の説明
不動産業務で難しいのが、借地権です。
今回はその説明になります。概論になります。
※ここのページで説明している借地権とは、旧法の借地借家法になります。(不動産で一般的にいわれているものになります。)
借地権の新法についてはこちらから
借地権の期間について
旧法の借地借家法の期間は
非堅固(木造)の場合・・・・20年間
堅固(鉄骨など)の場合・・・30年間になります。
新法借地借家法の場合は30年間となります。・・・あまり使われていません。
それ以外に定期借地権があります。(契約期間が50年以上の場合に可)・・・たまに使われます。マンション用地の場合など。
また、地上権、賃貸借の借地権があります。
今回は、旧法の賃貸借の借地権になります。
まずは、借地の各種承諾料についてまとめました
借地権の各種承諾料の一覧です。(木造住宅の場合)
| 借地権 各種承諾料 | 内 容 | 概ねの比率 |
1.譲渡承諾料
(名義変更料) | 借地権を売却するときにかかる承諾料 | 借地権価格×10% |
| 2.増改築承諾料 | 建物を建て直したり、リノベーションするときにかかる承諾料 | 借地権価格×10% |
| 3.更新料 | 借地契約の更新をする時にかかる承諾料 | 借地権価格×7% |
借地権は、売買、増築する時に、地主さんの各種承諾をとらなければいけません。
上記は概ねの概算になります。詳しくは続きを読んでください
借地権の価格割合について・・・俗に言われる、7割、3割、6割、4割などです
a.借地権の誤解
借地権についてですが、なじみのない方には良く誤解されていることがあります。
そのひとつに、借地権には権利がないと思われている方がいるということです。
借地権は売買できます
借地権の価格とは
借地権は「権」がついてある通り権利があります。
では、借地権の権利価格はどのくらいなのでしょうか。
計算方法としては、路線価図を使用します。

上の方にABCと記載されているところがあります。
ここで、借地権割合がきまります。
路線価図の欄に借地権割合70%、借地権割合60%と道路ごとにかかれています。
借地権割合を簡単に考えると
土地の権利=借地権+底地権と考えられます。
借地権とは土地を借りている方、「借りた土地の上に建物を所有している方の権利」
底地権は土地を所有している方の権利になります。いわゆる地主さんです。
たとえば借地権割合が70%の地域に1000万円の土地があると、次のような権利割合になります。
(土地価格1000万円)=(借地権700万円(借地権割合70%))+(底地権300万円(底地権割合70%))
になります。図で示すと次のようになります。
 借地権、底地権の割合を示す図の例
借地権、底地権の割合を示す図の例
借地権の承諾の種類
地主さまに承諾をとるには下記のものがあります
① 譲渡承諾(名義変更料)
② 増築、改造の承諾
③ 更新の承諾
承諾に伴ってそれぞれ承諾料が発生してきます。
① 譲渡承諾料(名義変更料)とは・・・借地権を売却する場合に発生する費用
借地権を売却する場合(借地人が、借地権を売却するとき)に地主さんの承諾を得なければなりません。そのときに発生するのが、譲渡承諾料(名義変更料)になります。
譲渡承諾料ですが、借地権価格×10%がおおむねの目安になります。
ところで、
a.借地権価格とは
借地権価格とは不動産を売却する時の価格になります。不動産売買契約書から算出する時もありますが、一般的には、計算により算出します。
b.借地権価格の計算方法
路線価格を基に①更地価格を算出し、②借地権価格を計算します。
例題) 路線価が300(千円/㎡)、土地面積 60㎡ 借地権割合70% のケースは?
A.300×60÷80%=22,500千円=2250万円が土地の更地価格・・・①。
2250×70%=1575万円・・・借地権価格になります・・・②。
※注意・借地権の承諾料は、更地価格をベースに算出することが多いですが、譲渡承諾料については、更地価格ではなく、借地権価格を基準で計算します。
※80%とは・・・路線価の価格は公示価格のおおよそ80%になります。
※実際は人気のエリア、逆に不人気のエリア、使いにくい土地などにより、土地の評価割合は変わります。
②.増改築の必要な承諾料とは、・・・建物を増改築する場合に発生する費用
a.建物の増改築とは
借地権に期間がありますが、建物が存続するかぎり、借地権は更新されます。建物を改築すると借地権の期間が延びることになりますので、地主さんに不利になります。そこで、承諾料が発生します。
ところで、建物の増改築とは、ちょっとしたリフォームにも適用するのでしょうか?
例えば、外壁の塗装工事は承諾料が必要かどうかですが、一般的に、外壁の塗装工事で承諾料が発生するケースはあまり聞きません。建物の存続期間は確かに伸びますが、あまりききません。私の意見ですと、塗装工事は5~7年周期に行ったほうがいいといわれていますので、木造建築物の存続期間が20年とした場合、3~4回は行った方が良い作業になります。確かに塗装工事をした方がしない方よりも、建物の存続期間は伸びますが、塗装工事は、建物の存続期間内に数回は行う作業でありますから、増改築の承諾料が発生するケースをあまり聞かない理由だと思います。
b.借地権の増改築の承諾料は
借地権の増改築の承諾料は、一般に更地価格の3~5%(借地権価格×10%)と言われています。
③.借地権の更新料とは
借地権の更新期間は、木造建物だと、20年ごとに、鉄骨造だと30年にごとになります。
借地権の更新料は概ね上記のとおりになります。
借地権の更新料=更地価格×3~5%(借地権価格×7%)
また、概論として、借地料を多く支払っていれば、更新料は少なくなり、借地料が少なければ、更新料は多くなります。
鉄骨やコンクリートなどの堅固な建物の場合は、借地期間が30年になりますので、
鉄骨造の更新料=更地価格×7.5%になります。
但し、上記更新料は、木造の建物(非堅固な建物)、借地期間が20年の場合である。
更新料を払わないでいると
更新料を支払う理由として、借地人は、借地権の権利確保したいのが一番の理由。地主さんは、毎月の地代では少ないため、更新料で補てんするのが、大きな理由です。
(地主さんの負担で一番おおきなところは税金だと私は思います。税金についてはいろいろと考えるところがあります。)
ところで、木造と鉄骨で契約期間が違うのは、建物の存続期間から来ています。どれぐらい建物がもつかということです。木造だと20年、鉄骨だと30年で建物が無くなるという考えからです。(建物がなくなると、借地権は消滅します)。しかし、実際には、建物は残っている。そこで更新の手続きが必要となります。
当社では、更新の手続きを行っています。
借地人の皆様には更新の手続きをするように勧めています。
不動産や弁護士の中には、更新料を支払わないという人がいます。これは、一見すると借地人の味方に見えますが、本当にそうでしょうか?
更新料をきちんと支払うことにより、地主さんと良好な関係を保つことができるのに、支払わないで良いという人は、長い目でみると、借地人さんの足を引っ張ります。
更新料についての専門家の意見は、むしろ、更新料は支払っておこうという結論になります。なぜなら、更新料を支払っていないと、様々な問題が生じるからです。一番大きい問題として、借地権の売買がしにい。(事実上、できない。)
なぜなら、借地の売買には地主の承諾が必要となってくるからである。他にもいろいろな問題点で借地人が不利になることが多い。そうならないためにも、更新料は支払い、権利の確定をすることが借地人のためであると私は考えています。(長い目で見た場合)。 賃貸物件については、更新料は支払うという判例がでています。おそらく借地権についても似たような判例がでると思います。その時、あわてないためにも更新の手続きはしておくことが望ましいと思います。
借地権の更新料についてを参照に。
3.借地権の実務
東京都荒川区のエリアですと、借地権割合が70%、底地権割合が30%になります。
借地権割合の方が割合が大きくなります。
なぜ、土地を借りている方が権利割合が大きいのでしょうか?
なぜ、大きいのかというと、借りている土地の上に建物を所有しているからです。
土地を使っているのは、借りている方だからです。
建物を所有していないと借地権は発生しません。または、消滅します。注意が必要です。
実務としては交渉がありますので、価格の変動はあります。しかし、ベースの上での交渉となります。
また、外国の方にはなかなか理解しにくく、借地権を嫌がる方は多いです。しかし、外国の投資家の方は理解している方が多いです。
※追加事項、訂正変更事項などがある場合は、更新により対応します)
(※不動産は地域によって扱いが異なります。)
(※企画情報館は荒川区の町屋で営業していますが、ここは借地の多い地域になります。参考例として考えてください。)
4.その他の追加記事
★2つの敷地にまたがっている場合(2015.7.29)
http://kikakukan.biz/post-3663
★定期借家契約について(借地とはことなります。借家の内容になります。)
http://kikakukan.biz/post-3670
★借地料はどうやって計算してだせばよいのか?
http://kikakukan.biz/post-4061
★借地料をあげてほしいといわれたら、地主さんがブラック地主だったら
http://kikakukan.biz/post-3921
★新借地法について
https://kikakukan.biz/post-6548/