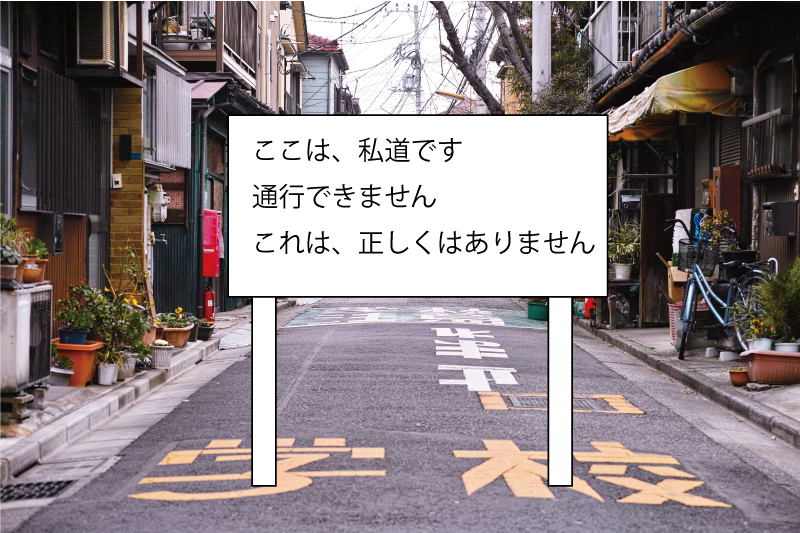私道(42条2項道路)のトラブルについて
東京都の私道についてのトラブルに下水道の問題があります。
地主さんの承諾と合わせて費用の問題があります。
下水道管理ができていないのは、東京都の責任。
下水道トラブルが私道で未だに起きています
上水道、ガス配管については、水道局、ガス会社で大体整備、把握してありますが、どうして
だか、下水道だけは、下水道局で整備、把握できていません。
私道という理由で整備されていません。
東京都が下水道を管理している限り、この問題がつづくと思います。
東京都は管理できないならば、区、市に管理をお願いするべきです。
私道の下水道の助成金・補助金について
しかし、東京都の対応を非難ばかりしていても仕方がありません。
下水道で問題なのが費用です。
この問題を解決するには、助成金制度を使う方法があります。
荒川区の助成金制度を使うのが現実です。
この制度は、42条2項道路以外にも、
①幅員1.2m以上の私道、②沿道の住民が4戸以上 ③公道または整備された私道に接続していること、④特定の所有者の通路ではないことの条件に合えば適用できるみたいです。
北区の助成金制度
墨田区の助成金制度
など、区によって対応が違います。
東京都では対応していません。東京都の無責任な対質があります。
しかし、土地所有者から印鑑なければ東京都下水道局、上水道、東京ガスがうごけないとは、どうかしていると思います。
下記は、5チャンネルからの掲載になります。
水道やガスの工事をするために嫌な隣人から許諾のハンコを押させるためのあの手この手を教えてつかーさい
水道の管を引き込むために掘削をしたいのだけど隣家の人がどーのこーの理由を付けてハンコを押してくれない。
もし掘るんだったらその私道50メ-トル全てを舗装しなさいとか建築工事は朝9時から5時まで。ゴミの集積所には住人の ゴミをだしてはいけないとか・・・・。
しまいにはあなたの説明を聞いていたせいで歌舞伎に見に行くのが遅れたからその料金を払えとかもうめちゃくちゃな人だし。
こういうふうにやったとかアドバイスをお願いします!
そもそもハンコがいるというのがおかしいと思うのだけど
またその人が近所にふれてまわってるスゴイキチガイの人です
隣の人は水道やガスで困って無いの?
隣の人は公道にも面しているとか?
単純に金か?
っていうと怒り出しかねないしネ
基本は何回も通うこと。 で、落としどころを探ること。
出来れば他業者にも同行してもらう。
埋設・接続管の工事内容を資料を見せながらキッチリ説明し、雑談を交えながら最後に完全復元を約束する。あとは掘削することで隣家にメリットのある、おみやげ工事をしてあげる話が出来れば……!
その土地の前?所有者に同行してもらうとか。
後でわかった事なんだけどその土地の施主さんが私道持っている人たちに 恨まれてるみたいなんで・・・正攻法は無理みたい
しかも苦情と称して施主さんに朝の5時くらいに電話いれたりと 狂ってる人です」
漏れは近隣5件にスムースに判子貰ったけど。 トラブッたら地獄屋根。お気持ち察します。
工事するのにいちいち判子必要なのが変だと思う 。東京ガス 水道局 どうにかしてくれ
そんなの見積もりの時点で、私道掘削の承諾必要です。って書いとけよ、、業者が承諾もらいにいく必要ないやろ~ そんなの施主か元請の営業マンの仕事♪
役所はどうにかしてくれんか
私道の持ち主に取ってみれば他人の水道管を通すなんて いやなものだよ。土地の価値が下がるしね。 俺のうちも私道があって近所の人が通り抜けするのを許してる
けど、ゴミは投げ捨てていくわ車は勝手に駐車するわで 。メチャクチャ。封鎖しようかと思ってる。
私道は廃止すべきだな 。高度成長時代の遺物だな。今もミニ開発は続いているようだが情けない罠 。
いまだに私道は自分のものだと勘違いしている人も多い
哀れで情けない(´д`)
袋路だと事実上私物的な使い方に成るな 困ったもんだ
実弾一件につき1~5万円用意するしかなかんべ。施主と相談してみ。
もしくは、オレが一回やったことあるのが、逆ギレ。
「じゃー!どうすりゃ承諾してもらえるんスカ!!」ってマジ顔で声を張ってみた。
興奮して、暴れ兼ねない素振りをしながら、
「判子押さないってことは、お宅は、将来建て替えも売買も出来なくなってもいいって言ってるのと同じことが分かってんのかよ!」と、
宣った後で、少し冷静になった口調で、「こういうことはお互い様なんだからサ……」
で、近隣を黙らせ納得させて判子押させたことはある。
役所に相談に行く。こういう鬼違いがいて、どうしても承諾書がもらえない。
どうすりゃいい?何か方法はないか?って聞いてみ。
承諾書をそろえて下さいとしか言えない、って役所が答えるのは分かってるけど、 相談というのはあくまでもポーズ。
困りはてていることを役所の担当者にアピールして、 工事場所と内容を担当者に記憶させるのが狙い。 困った顔して最低2回は役所に行くこと。
で、承諾書もらえないまま、近隣に、掘削工事をいついつからやります、ってカマシで一方的に通知する。
で、近隣が役所に駆け込んだら成功。役所も巻き込んで三者協議。 そうすっと多少、こっちのことを役所が大目に見てくれたし、 鬼違い近隣も無茶を言わなくなって、その後すんなり行ったこともあった。
役所が先導とるような形になればいいんだけどね
これとケースは違うが近隣が
「私道」と「私有地」とを勘違いしてて
えらく板違いな問答したことがあったなあ・・・・・
「私道」と「私有地」とを勘違いしててというか
ごねているひとはみんなそう思ってるよ
私道に一生懸命物置いてる奴いるし
いっぱいいっぱい車寄せてるキチガイも多い
焼き討ちしちゃえばいいか
役所に行ったけど全然あいてしてくれん
今度やる工事なんだが、私道の奥が申請人。
道路、専用通路共、手前の人(元医者)の所有なんだけど土地使用承諾書にハンコ押さなくて裁判になった。
工事は取水不良による増径工事なんだが既設管が鉛管である事などを主張して勝った。
そしてその元医者はハンコ押すのいやで逃げ回っていたが裁判所の回答書つけたら同じ効力がある、との事。
ま、これは申請人が弁護士に頼んで解決した非常にめずらしい例。
でも水道や下水など直接生活にかかわってくるものは優遇されるらしい。
認定道路だったら封鎖も何も出来ないよ。
第一オマエも人の私道を通って家に帰るんじゃないのか?
じゃないにしても私道なんてあちこちあるから知らずに通ってる罠。
いるんだよね了見の狭いケチが。
私道の所有者はみんな市に寄贈しる!
基地外は必ず私道にいるよね まるで配置されたみたいに
>私道の持ち主に取ってみれば他人の水道管を通すなんて
>いやなものだよ。土地の価値が下がるしね。
ぷっ!
そんな土地、道路以外に使い道あんの?
私道のある自治体は基地外の配置を義務付けてるらすい。
道路以外の使い道としては嫌がらせとか植木鉢置き場とか
役所も余計な私道もらうと維持管理責任が発生するから 貰いたがらないよね。
ごねてる隣人の土地が公道に面していなくて、私道を自分も含めた数人で共有しているなら脅すのが一番なのかな。 水道にしろガスにしろ、土地所有者の許可が無ければ工事 しないのは当たり前。やれば自分達が訴えられるからね。
工事のせいで家が傾いたから弁償しろなんて話もよくあ るくらいだから。
警察も所有者の許可を確認しなければ道路使用許可は出さないのが基本だしね。
そうかだから一区画にひとりずつキチガイが配備されているんだしらんかったYO
土地の価値が下がるだって~??
ちゃんと宅地以外の道路部分が道路として登記されてるなら
掘削・埋設工事で土地の価値が下がるなんてことあり得ないんですが。
価値が下がるってことは、おたくの私道部分て、
地目が道路になってなくて、固定資産・都市計画税をまともに払ってる、おばかサン?? てことになりますが、ヨロシイか??
その間違った思い込み、¥的にも常識的にもズレてる。ハズカシ…ιιι
てか、その感覚を貫くことが、確実に自分の土地の
資産価値を下げてることになる、って理屈、解る??
>俺のうちも私道があって近所の人が通り抜けするのを許してるけど、
いるんだよなあ~ こういう勘違いやろーが。
「私道」負担した時点でそこは「道」だから誰が通ろうが、おまえの「許し」などいらないの。
関係ねーんだよ!!
「ここは私道のため、勝手な通行は禁止します」
なんて間抜けな張り紙してるとこあるけど、あれと同類だな。
私道持分が単有なのか共有なのか、基準法の42条1項なのか2項なのか判らないのに、一概には言えないと思うのだが。
私道持分が
・単有
・共有
・1項道路
・2項道路
このどれかだったら、封鎖できるのか?
封鎖できません。
人の通行は出来るようにしとかなアカン。
みんながそれをやりだすと誰も公道まで辿りつけない。
そこを通らなければ家に帰れない人がいる以上、単有だろうが、42条2項だろうが封鎖など出来ない。
最近は車の通行さえ認められてる。
またこの理由なくても私道負担する理由は建築確認取る為の接道だろうし封鎖すると「道路に接してない建築物」になってしまう。
私道でも持分を持っていない場合は車の進入・人の通行を妨げることが出来る場合があります。隣地の接道がその私道を必要としていない場合です。
生活便宜上、人の私道を通った方が早いだとか楽だとかって理由で所有者に無断で抜け道的に使うことを拒否することは当然出来ます。
そんな土地なら初めから私道にしないで私有地として使う。
筆しようとする時に、事前に位置指定の申請だけしてある砂利道・未完成私道。
ったら、会社と施主も巻き込んで大騒ぎするしかなかんべ。
一人で悩んでてもラチあかんぞ。
ほとんどが農家(大地主)の所有で決して判子押してくれない。
よーく調べていくと、地主の親戚がプロパンガス屋だったりする。
東京23区内でも環八沿線はプロパンのアパートが結構あるのは
そのためです。
つうか、固定資産税すら払ってない土地に、なんの未練があるのやら。
私道問題って難しいですね。結局どうなったんでしょう。
ハンコ貰えたんですか?
排水管なら下水道法第11条の受忍義務でOK
「他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、
他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。」しかも
「当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、
他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に
告げなければならない。」ってわけで、告げればOK。同意不要のすばらしさ。
私道ってなんでみんな寄付しないの?
ていうか寄付を拒否する自治体ってなに?
私道の私設管が鉛だから行動にして市管にして欲しいんだけど。
寄付したくても色々な条件が揃わないと市でも貰ってくれないそうですよ。
たとえば舗装してあって幅が何メートルでなんたらかんたら。
それにしてもいにょう地の私道問題は尽きないですね。
私もハンコ貰うために調停準備中です。弁護士さん曰く、こちらが有利だそうです。
持分所有者全員の貰わなくてもいいはず。
適当に(字体を変えて)三文判で押しちゃいましょう。
ソース https://money4.5ch.net/test/read.cgi/build/1051518346/
いろいろと書いてありました。
やはり、私有地と私道の区別がつかない人がトラブルを起こす原因だと思います。
私道についての法律の定義があれば、よいのですが。
私が追いかけているのは、42条2項道路です
私道トラブル(42条2項道路)についは、色々と奥が深いです。