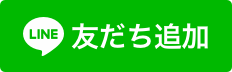最近は暖かい日が続いていますね。新生活が始まって早一か月、そろそろ慣れてくるころではないでしょうか。
話変わりますが、用途地域のことについて調べてみました。
1.用途地域の用途について
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:住宅、共同住宅、幼稚園、小・中・高等学校等) |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第一種低層住居専用地域適格建築物のほか、150㎡以内の店舗に限り建築可能) |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第二種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院等) |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:工場、パチンコ屋、カラオケボックス、料理店等を禁止) |
| 第一種住居専用地域 | 住居の環境を保護するため定める地域(例:劇場・映画館、キャバレー、個室付き浴場等を禁止) |
| 第ニ種住居専用地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止) |
| 準住居専用地域 | 道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止) |
| 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止) |
| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止) |
| 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域(例:個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止) |
| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、病院等を禁止) |
| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、キャバレー、個室付浴場等を禁止) |
2.用途地域の建蔽率について
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 |
30・40・50・60のうち都市計画で定める割合 |
| 第一種住居専用地域 第二種住居専用地域 準住居専用地域 準工業地域 |
50・60・80のうち都市計画で定める割合 |
| 近隣商業地域 | 60・80のうち都市計画で定める割合 |
| 商業地域 | 80 |
| 工業地域 | 50・60のうち都市計画で定める割合 |
| 用途地域の指定のない区域 | 30・40・50・60・70のうち特定行政が定める割合 |
3.用途地域の容積率について
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
50・60・80・100・150・200のうち都市計画で定める割合 |
| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居専用地域 第二種住居専用地域 準住居専用地域 近隣商業地域 準工業地域 |
100・150・200・300・400・500のうち都市計画で定める割合 |
| 商業地域 | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300のうち都市計画で定める割合 |
| 工業地域 工業専用地域 |
100・150・200・300・400のうち都市計画で定める割合 |
| 高層住宅誘導地区 | 都市計画で定められた数値からその1.5倍以上で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める割合 |
| 用途地域の指定のない区域 | 50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が指定する割合 |
4.用途地域の高さ制限について
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居専用地域 第二種住居専用地域 準住居地域 |
前面道路の反対側までの水平距離 × 1.25(m) 200%以下………………20mまで 200%超300%以下…25(20)mまで 300%超400%以下…30(25)mまで 400%超………………35(30)mまで |
| 近隣商業地域 商業地域 |
前面道路の反対側までの水平距離 × 1.5m 400%以下………………20mまで 400%超600%以下……25mまで 600%超800%以下……30mまで 800%超1000%以下…35mまで 1000%超1100%以下…40mまで 1100%超1200%以下…45mまで 1200%超………………50mまで |
| 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
前面道路の反対側までの水平距離 × 1.5m 200%以下…………………20mまで 200%超300%以下………25mまで 300%超400%以下………30mまで 400%超……………………35mまで |
| 高層住宅誘導地区 | 35mまで |
| 用途地域の指定がない区域 | 前面道路の反対側までの水平距離 × 1.25m、又は1.5m 200%以下…………………20mまで 200%超300%以下………25mまで 300超~……………………30mまで |