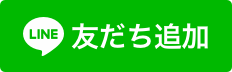不動産の売買物件のおしらせです。東京メトロ千代田線町屋駅から徒歩7分のところにある物件になります。
権利関係は借地権です。
土地の広さは101.42㎡(30.67坪)です。
荒川5丁目K邸へのお問合せ
■■東京メトロ千代田線 町屋駅から徒歩7分のところにあるK邸です。■■
下記よりお問い合わせください
03-3892-1421
yoneda@kikakukan.com
※詳細、不明なことなどについては、お気軽に問合わせください。
※また、空き状況、内覧希望日などについても、ご連絡お待ちしています。
■荒川5丁目K邸物件概要
| ■所在地. | 荒川区荒川5丁目 |
| ■交 通. | 千代田線 町屋駅 徒歩7分 京成線 町屋駅 徒歩 7分 都電荒川線 町屋駅 徒歩 7分 [map addr=”荒川区荒川5-33-2″ width=”200px” height=”200px”] [/map] |
| ■間 取. | 3階建 |
| ■権利の 種 類. | 借地権 |
| ■価格. | 2,980万円 |
| ■建物. | 平成8年築 居宅 木造3階建て 81.96㎡ |
| ■地 積. | 101.42㎡ |
| ■公法上 の規制. | 近隣商業地域 建ぺい率80% 容積率300% 準工業地域 準防火地域 |
■■ 東京メトロ千代田線 町屋駅から徒歩7分のところにあります。
plan
■■ 3階建 ■■ 日当たり良い ■■ ■■ ■■ ■■
■■■ 環境について ■■■ 町屋駅徒歩7分 ■■ 買物便利 ■■
■ ■ コンビニ近くにあります ■■ スーパー近くにあります。 ■■
■■■ M A P ■■■
■ ■町屋駅徒歩7分の立地。近くには商店街、コンビニなどあり、便利です■ ■
[map addr=”荒川区荒川5-33-2″ width=”400px” height=”400px”] [/map]■■■ 内覧希望等、お気軽にお問い合わせください ■■■
■物件のお問合せ
下記よりお問い合わせください
03-3892-1421
yoneda@kikakukan.com
※詳細、不明なことなどについては、お気軽に問合わせください。
※また、空き状況、内覧希望日などについても、ご連絡お待ちしています。